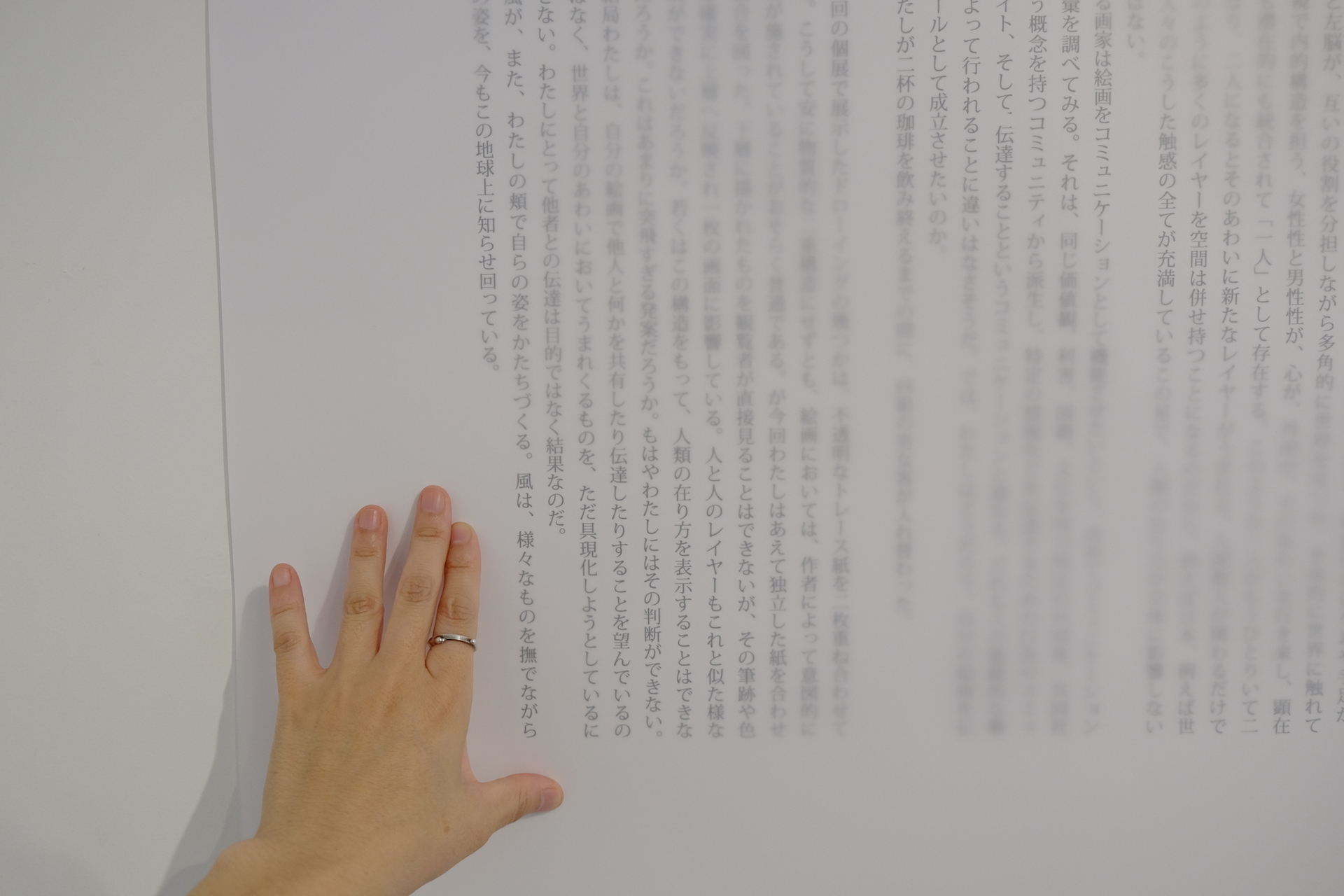
「そのあわい」
市街地からおよそ1時間ほど車を走らせた旧美麻(みあさ)村山間に珈琲店がある。最後、県道から脇道へそれて店を目指すが、その道は無舗装で急傾斜の林道だ。冬季は閉鎖され、夏はデコボコで、道の両側を鬱蒼とした樹木が生い茂る。「本当にこの道であっているのだろうか」と初めて行く誰もがたぶん不安になるような道。しかし、200Mほど上るとふっと視界が開けて、嘘みたいに穏やかな、そして、思ってもみないそば畑が広がる。県道からのアプローチと、このひらけた景色とのギャップに頭がシャッフルされ、一気に娑婆から切り離される。わずかな感嘆の声とともに下車し、しばし遠く向こうから吹くそよ風にあたる。そうして振り返ると、そこに店がある。店構えは、外装材を手のひらで撫でまわしたかのような抑揚があり、まるで女の体を何体も重ねたような柔らかさだ。
薄暗く落ち着いた店内の一角に腰をおろして、珈琲が運ばれるのを待つ。テーブル横の開かれた窓からは、そば畑を揺らした風が、今わたしの顔を撫でる。数本の細い髪の毛が、ゆったりと、耳元から頬にかけて風の強さにあずけてたなびく。これがこの風のかたち。
髪の動きを意識して観察すれば、風とわたしのあわいに有る触感が、透明な風を可視化する。不視覚なものは、視覚するものを介して、世界に現れている。わたしはわずかな触手を伸ばし、二つの世界の表層に触れて、知覚を具現化する。つまり、たなびく髪の残像から風を立体的に想像した脳が、不可視だった風の輪郭をあぶり出している。こうした、世界と世界のあわいをつなぐ触感や知覚作用はおそらく、詩人の言葉や、音楽家の創作にも通づるのだろう。つまり、そのあわいから藝術は派生していると謂える。
わたしたちの身体もこの両面世界を具体的に体現している。物質的な目や耳や手足が、右脳と左脳が、互いの役割を分担しながら多角的に世界を見つめ、多面的に世界に触れて、不可視で内的構造を担う、女性性と男性性が、心が、丹田が、そのあわいを行き来し、顕在的にも潜在的にも統合されて「一人」として存在する。このような一人がもうひとりいて二人になり、二人になるとそのあわいに新たなレイヤーがうまれる。人間数人が関わるだけでもこのように多くのレイヤーを空間は併せ持つことになるのだから、例えば日本、例えば世界の人々のこうした触感の全てが充満しているこの星で、人類の在り方が全体に影響しないはずはない。
ある画家は絵画をコミュニケーションとして機能させたいという。改めてコミュニケーションの語彙を調べてみる。それは、同じ価値観、利害、国籍、文化を持つ特定の共同体、共同社という概念を持つコミュニティから派生し、特定の情報などを伝達するための行為のコミュニケイト、そして’伝達することというコミュニケーションと連なる。どれも人の能動的な働きによって行われることに違いはなさそうだ。では、わたしはどうだろう。自分の絵画を伝達ツールとして成立させたいのか。
わたしが二杯の珈琲を飲み終えるまでの間に、4組の男女客が入れ替わった。
今回の個展で展示したドローイングの幾つかは、不透明なトレース紙を二枚重ね合わせている。こうして安に物質的な二重構造にせずとも、絵画においては、作者によって意図的に下地が施されていることがおそらく普通である。が今回わたしはあえて独立した紙を合わせて統合を図った。下層に描かれたものを観覧者が直接見ることはできないが、その筆跡や色味は確実に上層へ反映され一枚の画面に影響している。人と人のレイヤーもこれと似た様な説明ができないだろうか。若くはこの構造をもって、人類の在り方を表示することはできないだろうか。これはあまりに突飛すぎる発案だろうか。もはやわたしにはその判断ができない。結局わたしは、自分の絵画で他人と何かを共有したり伝達したりすることを望んでいるのではなく、世界と自分のあわいにおいてうまれくるものを、ただ具現化しようとしているに過ぎない。わたしにとって他者との伝達は目的ではなく結果なのだ。
風が、また、わたしの頬で自らの姿をかたちづくる。風は様々なものを撫でながら、その姿を、今もこの地球上に知らせ回っている。
